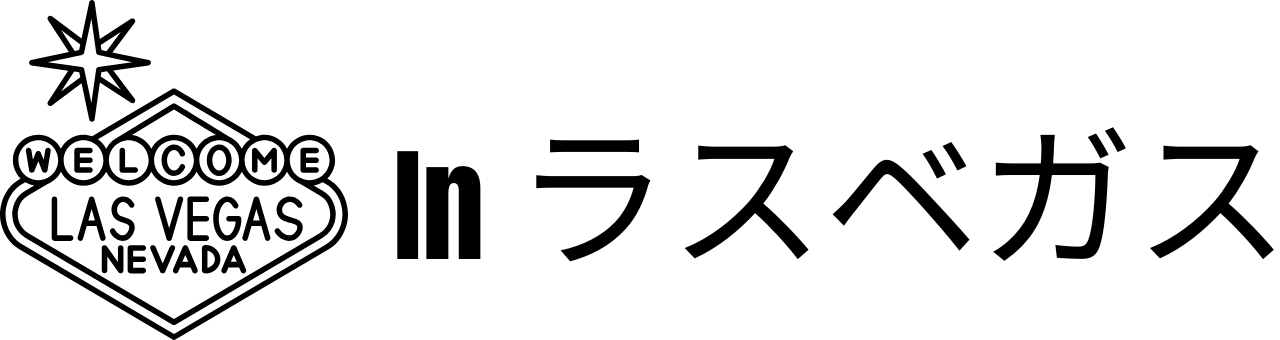ラスベガスの「はの」です。
2023年3月まで約6年間病気がちな義母と同居をしており、その後ホスピスケアを受けたのちに3か月前に他界しました。
老後のアメリカの医療介護システムにおいて義母に聞いても分からないことがあり、私自身このような疑問がありました。
・アメリカの老後が具体的にイメージできない。
・メディケアって何?
・シニアレジデンスって何?
・アメリカの緩和ケアとは?
勉強を兼ねて仕事が終わった後に専門家の情報や記事を参考に老後について調べてみると、このような事が分かってきました。
・アメリカの老後で抑えるポイント3点。
・最近よくあるメディカルコンシェルジュとは
・アシスタントリビングの様子
・アメリカのホスピスケアについて
家族として義母と一緒に経験した事を交えながら、こちらの記事を書いてみたいと思います。
老後までの3つのポイント

私自身30代半ば頃までは、老後の事はあまり考えていませんでした。
しかし義母との同居がきっかけで、この3点は若いうちから知っておくと老後はそれなりに安心して楽しく過ごせるのではないか、と考えるようになりました。
ソーシャルセキュリティー

ソーシャルセキュリティー制度とはアメリカ政府が運営している年金制度です。
アメリカに住んでいる人は移住と同時にその街のSocial Security Officeへ行ってソーシャルセキュリティーカードを受け取り、会社に入社すると必ずソーシャルセキュリティーの番号を雇用主から尋ねられます。
 上記の給料明細を見るとOASDI(Old Age, Survivors, and Disability Insurance)という税金が差し引かれています。これがソーシャルセキュリティー税です。
上記の給料明細を見るとOASDI(Old Age, Survivors, and Disability Insurance)という税金が差し引かれています。これがソーシャルセキュリティー税です。
アメリカ市民、またはアメリカに合法に住んでいて会社で働き給料を受け取る場合、従業員は給料から6.2%が自動的に差し引かれています。その額が上記の$76.66ですね。
会社側も 6.2% を支払ってくれていますので、合計12.4%のソーシャルセキュリティー税を会社と従業員が折半して支払っている計算です。自営業の場合は 12.4% を支払う必要があります。
これは国民の義務なので嫌でも差し引かれます。
この制度の主な内容としては、
・老齢給付(Retirement)
・障害給付(Disability)
・遺族給付(Survivors)
・補足的保障所得
(Supplemental Security Income)
この制度の大きな柱が老齢給付(Retirement)と言われています。
そしてアメリカでソーシャルセキュリティーを受給する為には3つのポイントがあります。
①受給資格:

・アメリカで合法に働く。
・ソーシャルセキュリティー税を支払う。
・40クレジット貯める。
ソーシャルセキュリティー制度ではクレジット制度が採用されており、2023年に$1,640のお給料を得ると1クレジットが得られ、年間で最大4クレジットまでを受け取ることができます。
$6,560の給料を受け取ると4クレジットが得られ、受給資格の40クレジットを得る為には10年間働く計算です。(2023年の情報)
②受給年齢:
現在は年齢が62歳になってから受給を開始することができます。しかし、その場合は満額を受給することはできず減額率が最大約25%です。1960年以後に生まれた人は、67歳以降に受給を開始すると満額が受給されます。
ソーシャルセキュリティーの受給年齢は62歳からですが、受給を開始する年齢によって受給額が異なりますのでその点は十分ご注意下さい。(2023年2月の情報)
③受給額:
ソーシャルセキュリティーの受給額は35年間の収入の平均で算出されます。
受給額は人それぞれ状況が異なりますので、ソーシャルセキュリティーのウェブサイト「my Social Security」のアカウントから現状やシュミレーションで確認することをおススメします。

尚、私の場合my Social Securityで現在の状況を見ると、満額受給ができるのは67歳、希望すれば62歳から受給することができると書かれています。(但し20年後にはこの年齢は上がっていると思われます)
既にリタイアしていた義母の年金は、毎月デビットカード(Direct Deposit)で振り込まれていました。食費・医療費・生活費・娯楽費・洋服はそこから賄います。
外出する頻度が少なくなったとはいえ、お洒落なお義母さんは室内で着る洋服やルームシューズにも気を使い、ネットショッピングで洋服を購入する時にはお手伝いをしていました。

アメリカで42年間看護師&シングルマザーとしてバリバリ仕事をしてきたお義母さん、アパートで一人暮らしをする場合にはソーシャルセキュリティーだけでは生きていけないと話しています。
(経済的に豊かな場合はこれには当てはらないと思います)
またラスベガスにはセミリタイアとして50代後半に本業を辞めて移り住んでくる人が多く、そのような先輩方の話を聞くと完全に定年を迎える(アメリカには法的に決められた定年の年齢はないので自分で決めるのですが)までにパートで働く人やソーシャルセキュリティーを満額受給できる年齢(67歳)に定年を設定したり、
または定年後も健康の為にパートなどで働き人生をエンジョイしている元気な方も多くいらっしゃいます。
同時に現在は受給額が35年間の収入の平均で算出されるので、いつどのタイミングで仕事を辞めようかと悩んでいる方もいらっしゃいます。

メディケア

メディケアは65歳以上の人や障害を持っている人が病院や医療費を賄うのを支援するためにできた国が運営する公的医療保険制度です。
メディケアの費用は現役世代の税金から支払われています。こちらは以下のように給料明細に記載されてあり、赤の部分にあるMedicareで毎月一定額が自動的に差し引かれています。

このメディケアは一般の保険会社と運用されており様々な医療サービスを提供しています。
メディケアの対象者:
・65歳以上、アメリカに5年以上の居住者
アメリカ市民権または永住権保持者
・65歳未満の障害を持つ人。
(一定の資格を満たす必要があり)
・末期の腎臓病または筋萎縮性側裂索硬化症を患われている人。
そしてこの部分が非常に混乱してしまいますが、例えば、内科、外科、眼科、歯科、療養施設などで、大きく4つのパートに分かれています。
メディケア4つの区分:
パート A:
入院/病院などの補償。(病院の施設使用、入院で掛かる費用)ソーシャルセキュリティー受給資格、政府機関で働き既定のメディケア税を支払ったことがある人は無料。働いた経験がない人でも配偶者のクレジットを利用してメディケアに加入することが可能。
パート B:
外来/医療などの補償。(内科・外科・眼科・歯科などの外来治療)有料
パート C:
メディケア認定企業が提供する民間の保険プラン(上記のパートA & B をカバーする代わりに、民間の保険会社が運用して補償)
パート D:
処方薬補償を提供。有料
利用者は自分に必要なものを選ぶことができ、年間の払い出し額が設定されていることもあります。
義母と同居していると、朝はあんなに元気だったお義母さんが「なんだか息が出来なくなってきた、いつもの体調と違うから救急病院に連れて行って!」ということがあり慌て近所の救急病院(ER)に連れて行ったことがあります。

そこでは血液検査・尿検査・点滴・薬の投薬・入院・医者診断・病棟施設利用などをして3日間の入院生活ののちに家に戻ってきました。
入院までしたものですから、それは高額な医療費を請求されるのだろうと思っていると全てメディケアで支払われたと聞き驚きを隠せませんでした。
投資

アメリカで老後を過ごす場合、ソーシャルセキュリティー、老後に掛かる生活費や医療費等を考えると国からの制度だけではやっていけないような気がします。
私は現在40代でこれから20年後はどうなっているのかは分かりませんが、アメリカの人口は日本と同様に減っていますのでソーシャルセキュリティーの受給年齢は上がっている可能性が非常に高いです。
いくら働き続けるとはいえども何が起こるか分かりません。しかし将来を悲観的に考えるより、今の私に出来るコトを考えて実践していることは以下の5点。
・フルタイムで仕事をする。(医療保険の為)
・少額でも投資する。
・健康に気を付ける。(運動・食事)
・ストレスをためず1日を楽しく過ごす。
・精神的&経済的な自立
ご存知の通りアメリカは医療費が高いので会社でフルタイムで働き医療保険のベネフィットを受けることが大事だということを病院へ行くたびに感じます。
そして会社で401Kのプランがあればそこから少額の投資から始め、まずは401Kとはなんぞや?という投資の一般的な(メリット&デメリット)勉強をしながら長期的な投資始めました。
お金の投資以外に大切なコトは自分への投資です。毎日の運動や食事には十に気付けて心の病気にならない為にもストレスをためずに楽しく過ごす、これに限ります。
いくら収入が高い仕事をしていても精神的にきついと長続きしません。心とカラダは繋がっていてどちらか一方が悪くても病気になってしまうと自分のカラダが教えてくれました。
そしてパートナーに依存して生きるのではなく、精神的かつ金銭的な自立は海外在住で家族が近くにいない環境にいるので常に心掛けていることです。(言葉では簡単ですが実行するのは難しいです)
退職後のラスベガスでの暮らし

老後のコトを考えると不安ばかり、、、。
ラスベガスで生活をしていると仕事をリタイヤする前に他州から移り住んでくる人や老後の住居としてラスベガスを選ぶ人によく出会います。そこで実際に経験した医療や施設を紹介します!
メディカルコンシェルジュ

メディカルコンシェルとは、一般的な医療サービスよりもより個人に合わせカスタマイズされた医療を行うサービス(コンシェルジュ)です。
お客様に合わせて医療サービスを提案したり専門医を勧める場合には予約を取ってくれる総合的なサービスを受けることができます。医療サービスを必要とする際にはプライマリーケア医として使用することもできるのです。
医師や施設によって異なります。こちらはラスベガスの目安です。(2023年現在の情報)
義母はアメリカ東海岸からラスベガスに引っ越しをした時に、医療機関に予約を取ってから医師との問診までに1か月~3か月と長い時間が掛かるので、それをお医者さんに相談したところこのMedical Conciergeを勧められました。
こちらを利用して医療機関に予約を入れて診察までの待機期間は早くて3日~数週間後です。
義母が行っていたラスベガスのMedical Conciergeは、血液検査のラボが入っていましたのでわざわざ血液検査の施設に出向く必要がなく同行者としても便利でした。
また専門の医者へ行く必要がある場合には受付の人が先方に予約を入れてくれたりと手厚いサービスがあり、そこで働いている人は患者さんの名前を全ての人が覚えているようで、看護師さんにあうと「こんにちは!OOさん、元気でしたか?」とそこで働いている人のみんなから声を掛けられるコミュニティーのようなものがありました。
また先生は物腰が柔らかい人で、義母の話を「うんうん、そうだね~」といって聞いており、義母の話をじっくりと聞く姿勢や医療ケアの提案をする際のカスタマーサービスはそれは見習うものが多々ありました。
Medical Conciergeへ行く理由として
・サービスや対応の違いがある。
・予約までの待ち時間が短い。
・コミュニティーのような繋がりがある。
こちらのサービスは年齢に関係なく1年間の年会費を払うと誰でもサービスを受けることができ、30代の友達夫婦もこのサービスを利用しています。
老後に限ったことではありませんが義母に同行してメディカルコンシェルドクターへ行った時には、シニアの方が多くこのオフィスがある場所は収入の高いといわれる地域にありました。
シニアレジデンス

特にラスベガスには税金対策や気候の関係でリタイア後に他州から移り住んでくる人が多く、55歳以上が購入できる住宅施設シニアレジデンスや55歳以上を対象とした住居アパートなどがあります。
こちらは老人ホームではなく、経済的に裕福な方々の為の住まい&コミュニティーです。
シニアレジデンス
ヘンダーソン市:7か所
ラスベガス:11か所
ノースラスベガス:2か所
こちらもラスベガスは比較的治安の良い(収入が高い)エリアにあります。
友人のご両親は50代後半にラスベガスにシニアレジデンスに一軒家を購入し、リタイア後は他州にある本家とラスベガスを行き来する生活をしています。
冬場はラスベガスで過ごして夏場はシカゴで暮らす(私にとっては)夢のような生活で、ラスベガスで暮らす数か月間は他州から友達や子供達が遊びにきたり、
ラスベガス周辺にある国立公園を巡ったり、週末にはホテルで行われるコンサートに出かけたりと人生を大いに楽しんでいる様子がこちらまで伝わってきます。
このシニアレジデンスに遊びに行くとこのような施設がありました。
・ゴルフ場
・プール
・ジム
・スパ
・レストラン
・BBQエリア
・バンケットルーム
・コンシェルジュ
こちらのコミュニティーセンターでは、毎週どこかで趣味のクラス等が行われており、手芸・トランプ・ビンゴゲーム・ヨガなどを楽しむ元気な方々がいらっしゃいました。
ラスベガスが選ばれる理由
・気候
・エンターティメント
・レストラン
・アクティビティー
・観光施設
Assisted living(アシステッドリビング)

Assisted living(アシステッドリビング)とは、高齢者や障害を持つ人々が家族と一緒に暮らすような雰囲気で過ごす集合型の住宅施設。
こちらに住む人は基本的には自分自身で身の回りの事ができることを前提として生活を送りますが、必要なときには施設から介助を受けることができます(有料)。
共用のスペースやカフェテリアなどでは、そこに住んでいる人同士のコミュニケーションを図る場にもなっていますので、閉鎖的なイメージは全くありませんでした。
施設の内容
・カフェテリア
・美容院
・図書室
・映画のシアター
・ランドリールーム
・アクティビティルーム
・ゲームルーム
・フィットネス/セラピールーム
・シアター
・プライベートダイニングルーム
お部屋
・バリアフリー
・スタジオタイプの1ベッド
・簡易キッチンと専用バス付き
・個別制御の冷暖房システム
・24時間緊急通報システム
エンターテイメント
・ライブミュージック
・ビンゴ大会
料金
施設によって料金は異なると思いますが、義母の施設は1か月約$3500程でした。入居を決めた時にその部屋をホールドする為に1か月分の家賃を前払いし、また退去する時には翌月分の家賃を支払ったようです。また洗濯や病院への送迎が必要な場合は有料のサービスがありました。
サービスの内容
・入浴などの日常生活動作の介助
・看護スタッフが24時間常駐。
・投薬モニタリング
・レストランスタイルの食事(1日3食と軽食有)
・毎週1回ハウスキーピング
・有料のランドリーサービス
・有料の診察、食料品の買い物、銀行への定期送迎サービス
こちらにはご夫婦で入居されている人もいて老後を楽しんでいる雰囲気がありました。
また施設には看護師さん(RN)が一人常駐しており健康相談などはその人に相談ができるようなシステムがあり、家族としても安心して義母を任せられて、毎週金曜日は元気なハウスキーピングのスタッフさんが部屋にやってきて、義母への声かけや世間話をしている姿を見るとまるで家族のようでした。
ホスピスケア

1. Routine home care(在宅ケア)
在宅ケアには、以下のようなサービスが含まれます。
・看護サービス:薬の投与、創傷管理、感染予防、病状のモニタリングなど
・医療介護サービス:理学療法、作業療法、言語療法、栄養管理など
・心理的な支援:心理的な苦痛の緩和、患者と家族のカウンセリング、死に直面する不安の軽減など
・社会的な支援:ボランティアによるサポート、社会福祉事業者への連絡、緊急時の対応など
2. General inpatient care(一般的な入院診療)
General inpatient careは、患者さんが緊急の医療ケアを必要とする場合に提供される在院ケアの一つです。
痛みの管理や身体的な苦痛の緩和、心理的な支援、社会的な支援などを必要とする場合には、一般的に在宅でのルーチン・ホーム・ケアが提供されますが、痛みや症状が深刻な場合や緊急の医療介入が必要な場合には、患者さんは入院して医療ケアを受けることができます。
以下のようなケアが含まれます。
・痛みの管理
・経口摂取が困難な場合の養分補給
・身体的な苦痛の緩和
・終末期医療
・心理的な支援
・社会的な支援
患者さんの状態が安定したら、またルーチン・ホーム・ケアに戻ることもできるようです。
3. Continuous home care(継続的在宅ケア)
Continuous home care(連続在宅ケア)は、緊急の医療ケアが必要な場合の在宅ケアです。
以下のようなケアが含まれます。
・痛みの管理
・呼吸器の管理
・嚥下の管理
・養分補給
・身体的な苦痛の緩和
・終末期医療
・心理的な支援
・社会的な支援
4. Respite care(レスパイト)
Respite care(レスパイトケア)とは、在宅介護を受けている家族介護者の疲れを癒すための短期的なケアサービスです。
在宅介護を受けている方は、家族介護者によるお世話や看護介添え日常生活の手助けなどを受けながら過ごすことが多く、介護者の負担が大きくなることがあり、その為家族の介護者が一時的に休息を取ったりリフレッシュするためにレスパイトケアというサービスがあります。
レスパイトケアは、通常、数時間から数日間の期間限定のサービスで、一時的に患者さんを施設などに預けることができます。また、在宅介護を受けている方の家庭に専門の看護師やケアマネージャーを派遣して、一定期間の間、家族介護者の代わりに介護サービスを提供することもあるようです。
レスパイトケアには、以下のようなケアが含まれます。
・日常生活の援助
(食事、入浴、着替え、トイレなど)
・医療的ケア
(薬の管理、看護、医療機器の管理)
・社会的ケア
(コミュニケーション、レクリエーション)
義母は自分で身の回りのことができるうちは、在宅でケアを受けていました。毎週1回Register Nurseの訪問看護士さんが自宅へやってきて、健康の相談や簡単な体調チェックを行っていました。
それとは別に介護士さんが自宅へやってきて入浴のサポートを行ってくださいました。
この在宅ケアを約半年ほど受けたのち、ラスベガスにあるグループホームへ入居し、そこでホスピスケアを受けました。ここのホームへ入居する時は、ソーシャルワーカーが自宅にやってきて義母の経済状況や希望を聞き、義母が入れるところがグループホームでした。
これが約1~2週間で話が進み、ちょうどグループホームの施設で空きが出ているので選んでいる時間はなくそちらに決め、そこの施設のオーナーさん(個人経営でグループホームを3軒所有している看護師さん)が直接我が家へやってきて施設の案内を受けました。
グループホームケア

24時間の見守りケアが必要になってきたこともあり、お義母さんはグループホームでホスピスケアを受けながら暮らすことになりました。
オーナーの女性(30代)は彼女のお母さんがフィリピン出身でアメリカ育ちということで、実際にホームへ行くとスタッフの皆さんはフィリピンご出身の方々、お義母さんや私達夫婦にもとてもフレンドリーに接してくれました。
お義母さんにこのホームはどうかと尋ねると「みんな親切でいい人ばかりなので良かった、私は運がいい」と話していました。
ここはラスベガスの普通の住宅街にあり外見からはグループホームとは分からないほどで、入居者の患者さん5~6人が一緒に暮らし24時間のケアサポートがありました。
料金はエリアや部屋の広さや施設の築年数などで異なると思いますが、$2500~$3000前後です。
予算の関係で1部屋に2人のルームシェアで、これまで抱いていたグループホーム=暗いイメージとは違って驚きました。
そこにはフレンドリーのハウスマネージャー兼料理担当の人がいつも義母に「Hi, do you need anything?」と頻繁に声を掛けている様子、義母曰く「ここで働いている人はみんないい人よ!」と話をしていました。
私達もその様子を見てホッとしていて、家族のようにみんなに囲まれて生活をするのがグループホームケアなのかということを知り、2023年9月に義母はこのグループホームで天国へと旅立ちました。
まとめ

(写真:義母が元気な頃に行ったザイオン国立公園)
今回はアメリカの老後についてソーシャルセキュリティーのシステム、メディケア、アメリカの老人ホーム、シニアレジデンスについてご紹介させて頂きました。
こちらの情報は2023年2月の現在のモノですので今後は制度が変わる場合があります。また私は専門家では御座いませんのでこちらの情報はあくまでも参考としてお知りおきください。
「ココの情報は間違っているよ!」がありましたらご指摘頂けると助かります。宜しくお願いいたします。
最後になりますがアメリカでの老後を不安に思っていても仕方がありませんので、今日できることを精一杯楽しく生きる!で1日を過ごしていきたいと思います。
こちらの記事がお役に立てば幸いです。
記事の感想やご意見・ご要望はツイッター(X)DMからお願いします。